中学生の頃、僕はずっと音楽室に入り浸っていた。放課後のピアノは誰にも邪魔されず、鍵盤に触れると時間が溶けていくような感覚があった。その理由の半分は、音楽の先生の存在だ。落ち着いた声、優しい所作、静かに笑う横顔。大人の女性を意識し始めたのはあの頃だった。
ある日、練習を終えた僕に先生が言った。
「あなたの音、すごく好き。もっと聴かせてほしい」
その一言を、当時の僕は 告白 に近い響きとして受け取ってしまった。「好き」という言葉が胸に響き、家に帰っても耳の奥で残響していた。今思えば教師としての評価だったのだろう。でも若かった僕は舞い上がり、「もしかして先生は僕に好意があるのでは」と勘違いした。
それからも先生は時々優しい言葉をくれる。
「あなたの演奏は丁寧ね」
「話すと落ち着く」
「相談があればいつでも来て」
今ならわかる。そのどれも恋愛ではなく、成長を支えるための言葉だ。でも十代の心はシンプルで、褒められれば特別な意味があるように錯覚してしまう。僕はいつの間にか「何度も告白された」と思い込むようになった。実際は告白ではなく、ただの信頼と指導だったのに。
卒業して何年も経ってから、その誤解に気づいた。大人になって改めて先生の言葉を思い返すと、そこには恋ではなく「教師として生徒の可能性を信じる眼差し」があった。美化していたのは僕の方だった。
でも、その勘違いが悪いわけじゃない。
むしろ恋愛観の原点になったと思っている。
優しくて、ちゃんと話を聞いてくれて、急がず寄り添う人に惹かれる。
出会い系で年上女性が気になるのも、穏やかな対話を求めるのも、多分あの頃の記憶と繋がっている。幼い恋心でも、誰かに大切にされたと感じた経験は、男にとって大きな骨格になる。
恋は相手の気持ちを知る前に、まず自分の中で音が鳴る。
その勘違いの音を恥じる必要はない。未熟でも、好きだと錯覚した瞬間が人生を動かすこともある。
今も出会いを探しながら思う。
先生がくれた言葉は、恋ではなく人生への旋律だったのだと。
恋は成就だけが価値じゃない。
心に残る音があるなら、それで十分だ。
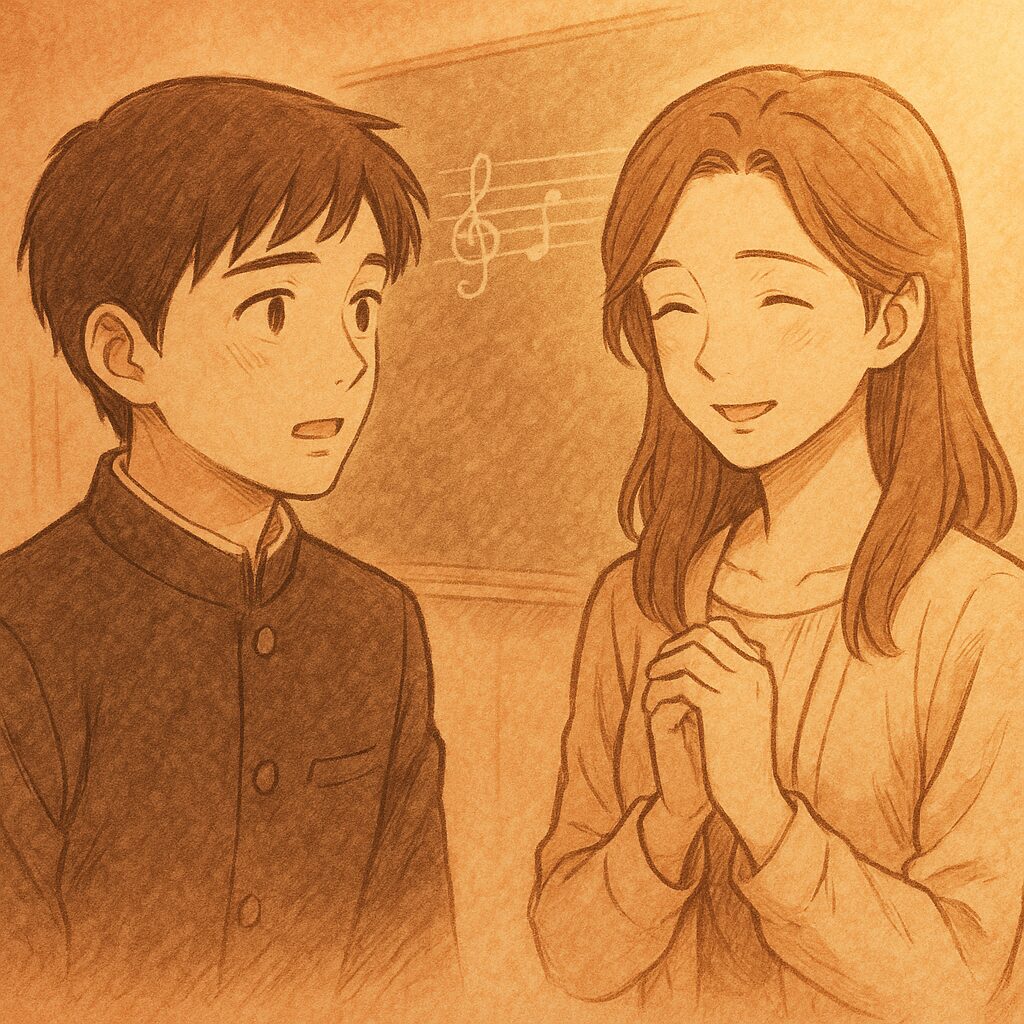


コメント